子どもが「ちょっと違うかも?」と感じる行動をしているとき、どうしていいかわからないことが多いと思います。もし「発達障害かも」と感じた場合、何をすれば良いのかを具体的に分かりやすく説明しますね。
1. まずは専門の医師に相談しよう
子どもの様子に不安を感じたら、 専門の医師に相談すること が最初のステップです。小児科の先生でも良いし、発達障害を専門に診ている病院でもOKです。
- 予約の取り方:まずはインターネットで「発達障害 クリニック」や「発達支援 病院」などと検索し、近くの病院を見つけます。その後、電話かWebで予約を取りましょう。人気のある病院だと、予約が 半年以上待つこともある ので、できるだけ早めに予約をしましょう。
- 待機期間:もし待機期間が長くても、焦らずに待ちながら、他にできることをしておきましょう。たとえば、地域の 子育て支援センター や 発達障害について学べる本 を読んで勉強しておくと、不安が少し軽くなるかもしれません。
2. 発達のチェックを受ける
専門の医師に相談すると、 発達のチェック(評価) を受けることになります。これで、子どもの発達がどうなっているかを見てもらえます。
- チェック内容:専門の医師やスタッフが、子どもがどんな言葉を使っているか、どんな動きができるか、他の子どもと比べてどうかを見ます。たとえば、年齢に合った言葉を話せているか、他の子と遊べているかなどを観察します。
これにより、もし発達障害がある場合、その症状がどれくらいなのかが分かり、どんな支援が必要かがわかります。
3. 支援を受けるために準備しよう
発達障害が診断された場合、子どもにどんな支援が必要かを考えます。学校や保育園、地域での支援を受けることができます。
- 学校や保育園での支援:例えば、 特別支援学級(特別に支援が必要な子どもたちが通うクラス)に通ったり、個別にサポートを受けたりすることができます。まずは、学校の先生に「支援が必要かも」と相談しましょう。
- 療育施設:もし子どもがまだ小さい場合、 療育施設 という場所で、遊びながら発達をサポートしてくれます。近くの療育施設について、かかりつけの小児科や地域の支援センターで調べてもらいましょう。
4. 親もサポートを受けよう
子どもだけでなく、親もサポートを受けることが大事です。発達障害について学ぶことで、どうサポートすれば良いかが分かりやすくなります。
- 親のサポートグループに参加する:同じような悩みを持つ親たちが集まる 親の会 や サポートグループに参加すると、他の親と情報交換でき、気持ちが楽になります。
- 専門家に相談する:カウンセリングや心理士に話を聞いてもらうことも大切です。自分の気持ちを整理するために、話を聞いてもらいましょう。
5. 早めに対応することが大事
発達障害がある場合、 早めに対応することが重要 です。早くから支援を受けることで、子どもはより良い成長ができる可能性が高くなります。できるだけ早く専門家に相談し、必要なサポートを受けましょう。
最後に
発達障害かもしれないと思った時、何から始めたらいいか分からないかもしれません。でも、最初に専門医に相談し、診断を受けることで、次に何をすれば良いかが見えてきます。早めに支援を受けることで、子どもの成長をサポートできるので、心配せずに一歩踏み出してみてください。最初の一歩が、子どもの未来を大きく変えるかもしれませんよ!

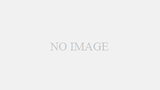
コメント